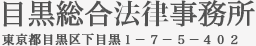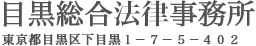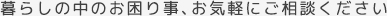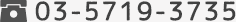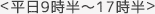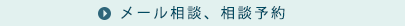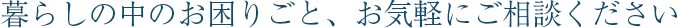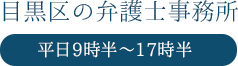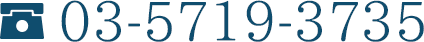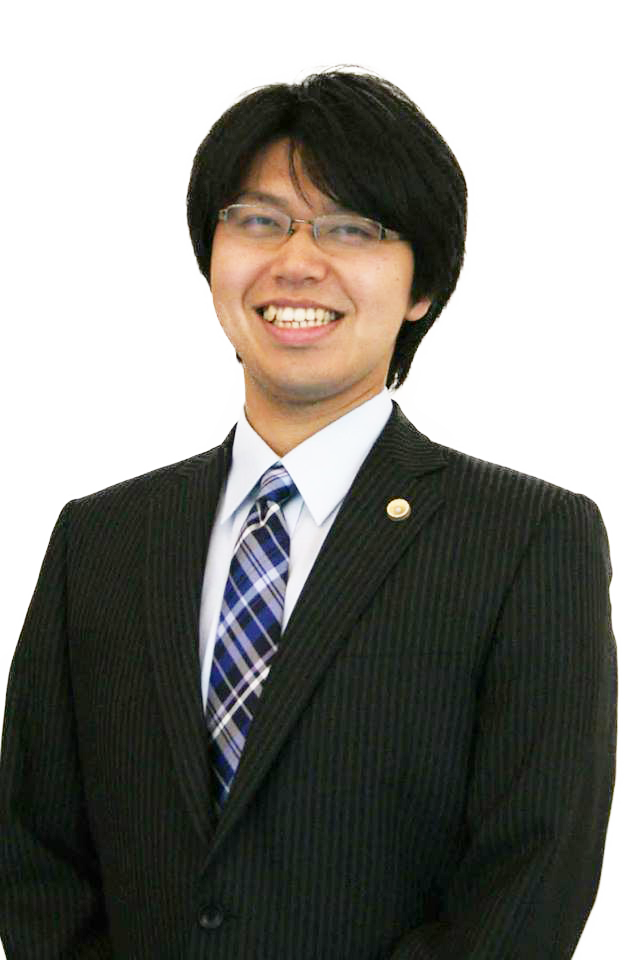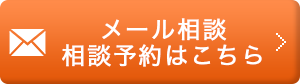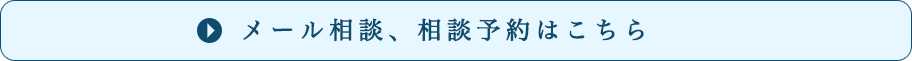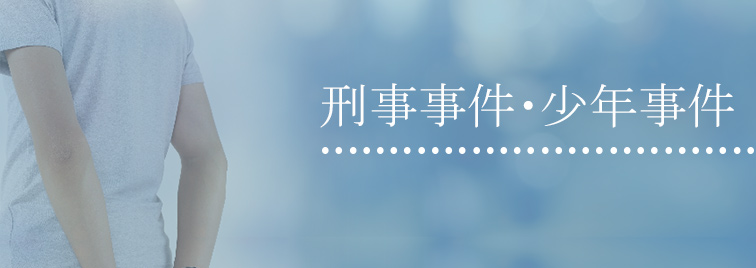
勾留を争う弁護活動
勾留とは
警察官が被疑者を逮捕すると、48時間以内に事件を検察官に送ります(送検)。
送検されてから24時間以内に検察官が勾留請求をして、それに対して裁判官が勾留決定をすると、勾留請求の日から10日間の範囲内で身体拘束を受けることになります。
その後、検察官が勾留延長請求をして、裁判官がそれを認めると、最大プラス10日間の身体拘束を受けることになります。
勾留の争い方
勾留は、一般に、証拠隠滅又は逃亡を疑う理由があるときに認められるものなので、勾留を争う際には、これらのおそれがないことを主張することになります。
例えば、証拠隠滅に関しては、被害者や目撃者の連絡先を知らないため働き掛けができない、対象となる証拠物が既に差し押さえられている等で、証拠隠滅を疑う理由がないと主張することが多いです。
また、逃亡に関しては、養っている家族がいる、定職に就いている等で逃亡するおそれがない等と主張することが多いです。
監督者がいること、示談を予定していることも、証拠隠滅や逃亡のおそれを低くするものといえます。
勾留を争う流れは、①勾留請求をしないように検察官に働き掛けること、②勾留しないように裁判官に働き掛けること、③勾留の取り消しを求めること(準抗告)という順番となります。
まず①勾留請求をしないように検察官に働き掛けることがあります。
検察庁に意見書を事前に送り、担当検察官と話をするのが通常です。
検察官が勾留請求をするということになると、次は②勾留しないように裁判官に働き掛けることです。
被疑者が裁判所に連れていかれる日に(勾留請求の翌日が多いです。)、裁判所に意見書を事前に送り、裁判官と面会又は電話で話をします。
それでも裁判官が勾留をした場合には、③勾留の取り消しを求めることになります(準抗告)。
②に比べると、認めてくれることは少ないように感じます。
勾留延長の争い方
勾留を延長する理由としては、一般に、必要な捜査が終了していないこと、例えば被疑者や関係者の取り調べ等が終了していないこと等が挙げられます。
したがって、勾留延長を争う際には、当該事案のために必要な捜査は当初の勾留期間で足りることを主張することになります。
実際の捜査状況については(検察官が教えない限り)弁護士は知り得ないので、取り調べ状況を被疑者から聴き取ることにより推測せざるを得ないところがあります。
当番弁護士制度
以上のように、勾留を争う弁護活動は色々なことを短期間でしなければならないものです。
多くの弁護士は急に頼まれても(逮捕は通常いきなりです。)、対応できる時間がないことが多いのではないかと思います。
そのためもあり、弁護士会が当番弁護士制度というものをもうけています。
当番弁護士制度は、弁護士が1回無料で逮捕された人に面会に行く制度です。
逮捕された人やその家族は各地の弁護士会に当番弁護士の派遣を要請することができます。